« 青いロマンス。 | メイン | [DTM作品] フライト・レコーダー »
2008年3月20日
ゆめか、うつつか。
断片的に1時間ぐらい眠っては目覚めるという時間を過ごして仕事を終えた一昨日。けれども危うげな状態にあることをわかっているのは自分だけだったと思います。ぼくの内面的だけにめまぐるしい思考の暴風が吹き荒れていたとしても、外側に存在するのは、おだやかなハル。
さすがに睡眠が不足していると、ふらふらする。というよりも、ふわふわします。ふあん(不安)という言葉は、地に足の付かない状態を表すのに適切かもしれません。通勤電車のなかで、オフィスの静けさのなかで、どこかまだ夢が続いているような気がして、この気持ちは危険だなとも思った。
リアリティがない、というのではないですね。むしろすべてがリアル。ただしその現実は夢という大きなカッコで括られている感じ。ぼくの視界にないところ、つまり死角で<これは夢ですよー>というプラカードをあげているひとがいるのだけれど、さっとそちらを向くとすばやくプラカードを下げて知らん顔をしているような、どっきりカメラ的な現実。そんな心象の風景がありました。
仮に夢の世界と現実の世界があったとします。夢の世界は曖昧模糊としていて、目が覚めてしまえば消えてしまう。消滅することを前提とした美しい世界です。一方で現実の世界は精彩があって騒がしいけれどもあたたかくて、いつまでも継続している。そしてそれぞれの世界の住人がいる。
夢の世界の住人が現実を訪れたらどうでしょう。きっとそのリアリティに眩暈を感じる。エッジが際立っていて、論理のつじつまが合って、よくも悪くも消滅することがない世界。愛しいものに触れることもできるし、五感のすべてを動員して世界を感じ取ることもできる。その確かさに目が眩む。
でも、しばらくすると夢の世界の住人は所在のなさに落ち込み、現実の世界のなかで消耗していくような気がします。夢の世界の住人は、ぼんやりと影が薄くなって、やがて大気の粒子として消えていってしまうのではないか。誰にも知られずに、また知られたいとも思わずに。
一方で、現実の世界の住人が夢の世界を訪れたら何を感じるのでしょう。夢の世界は曖昧で、茫洋としていて、何が起こるかわからない。しかしながら快楽的で、アドレナリンが噴出するほどスリリングで、できればずっとそこにいたいぐらいに魅力的。
たとえばこんな場所です。河が流れていて、屋形船がけばけばしい電飾の光を水面に散りばめながら静かに運航している。煌いてる原色のあかりが水面でゆらゆらと揺れている。河のほとりには狭い舗道があって、大切な誰かとそこを歩いている。気配だけを感じる。そのひとの存在はあまりにも儚くて、大切すぎて、手を握ることさえできない。触れたらその指の先から、粒子が分解していきそうな予感がある。
しかし、夢の世界には制限時間があり、現実の世界に帰らなければなりません。まるで舞台セットを片付けるように、夢の世界の記憶はすべて失われてしまうわけです。しっかりと網膜に焼き付けておきたいと思うのだけれど、そう思った途端に世界の輪郭がますます曖昧になっていく。写真を撮ろうとしても、焦っているからピンボケでさまにならない。実体の周辺に漂う雰囲気のようなものだけを残して、夢の世界はゆっくりと消滅していきます。そして自分だけが現実世界に取り残される。

睡眠不足
の
意識のなかで
そんな幻想を思い浮かべました。
ぼくらの世界は、儚く、
脆い。
さて。
そろそろ東京でも、さくらの開花宣言でしょうか。
卒業と入学という終わりと始まりが混在する切ない季節ですが、街を行き交うひとはどこか賑やかです。鞄にしまい込まれたままでしたが、地下鉄の駅で配布されているフリーペーパー「metropolitana」の3月号は「桜色の夜に酔いしれて」でした。
夜桜の写真を大きくレイアウトして、さくらを題材としたいくつかの小説が取り上げられています。水上勉さんの「櫻守」。渡辺淳一さんの「桜の樹の下で」。村上春樹さんの「ノルウェイの森」における夜桜の描写など。
そういえば花見の描写で思い出したのは、川上弘美さんの「センセイの鞄」にある花見の描写でした。どこか甘酸っぱいものがある場面で、あらためて本棚から引っ張り出して読んでみました。いま文庫になったかと思うのですが、ぼくが持っているのはハードカバーです。
 | センセイの鞄 川上 弘美 平凡社 2001-06 by G-Tools |
美術の石野先生(女性)に誘われて、センセイこと松本春綱先生は主人公である大町月子(38歳)を花見に誘います。花見の場所で、月子は同級生の小島孝に出会う。小島孝は、月子の友達の鮎子と結婚してその後は離婚していた。その元配偶者だった鮎子は、高校時代から石野先生に憧れていました。ややこしいスクェアな関係なのですが、松本先生に誘われておきながら月子さんは花見の宴のあいだに小島孝と抜け出して、バーでワインをくるくる回しながら飲んだりしています。松本先生を置き去りにして。
けれども月子の心は、松本先生にある。だから次のように気付きます(P.134 単行本)。
月が、空にかかっていた。 「月子の月だな」小島孝が空を見上げながら、言った。センセイならば、まず言いそうにないせりふである。センセイのことを突然に思い出して、驚いた。店の中にいるときには、センセイのことはあわあわと遠かった。小島孝がわたしの腰にかるくまわしている腕が、突然重く感じられた。
そして、疲れた、年だ、という小島孝に反論しながら、次のように考えます。
わたしはセンセイのことを思っていたのだ。センセイが自分のことを「年だ」などと言ったことは、一度もない。気軽に「年」をもてあそぶ年齢でもないし、質でもないのだろう。ここに、この道に立っている今のわたしは、センセイから、遠かった。センセイと私の遠さがしみじみと身にせまってきた。生きてきた年月による遠さでもなく、因って立つ場所による遠さでもなく、しかし絶対的にそこにある遠さである。
この遠さに共感。それはバーにおける現実と、花見という一種の夢のような儚い場所における距離であるともいえます。あるいは孤独なものと孤独なものの距離かもしれない。「万有引力とは/ひき合う孤独の力である」という言葉はぼくが好きな谷川俊太郎さんの「二十億光年の孤独」の一節なのだけれど、遠いからこそ惹かれるチカラも強まるのかもしれません。
小島孝とは身体的に密着しているのに、月子はそこからは位置関係だけでなくすべてにおいて遠いセンセイのことを思っています。ぼくは最初にこの部分を読んだときに、じれったさのようなものを感じました。なぜ小島孝と付き合ってしまわないんだ、と。月子は実際にかなり揺れている(不意打ちで小島孝にキスをされてしまう)。この、淡いものぐるほしさ(正気の沙汰ではない感情)が、花見という儚いシチュエーションと相まって、なにか痛切なひりひりするような感覚を伝えてくれます。
月も桜も、一種の狂気の象徴として扱われるものかもしれないですね。桜といえば、映像では北野武監督の「Dolls」の桜のシーンを思い出しました。
 | Dolls[ドールズ] 北野武 バンダイビジュアル 2007-10-26 by G-Tools |
社長令嬢との縁談のために付き合っていた彼女との約束を破ってお互いに壊れてしまうふたり(西島秀俊さん、菅野美穂さん)が満開の桜の下を、「つながり乞食」として赤い布でつながれながら歩いていくシーンが印象的でした。YouTubeから。
公式サイトのFlashもかなりきれいです。オープニング部分の桜のシーンをキャプチャーしてみました。音楽は久石譲さん。
■Dolls 公式サイト
http://www.office-kitano.co.jp/dolls/
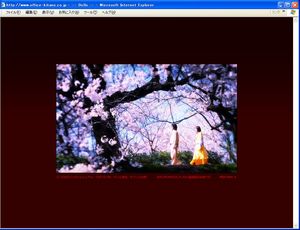
愛情は憎しみをともなう、というか、暴力のなかにやさしさが存在することもあると思うのですが(ちょっとSM的な思考かもしれませんけどね)、北野武監督の暴力的なまでに静かで美しい映像に衝撃を受けました。
と、睡眠不足によって覚醒された眠りのような状態で感じたことをそのまま表現してみたいと思ったのですが、なかなか難しいものです。であれば春の空気に包まれながら、ぼーっと花を眺めてしあわせな気分になるのもいいかな、などと。
投稿者 birdwing : 2008年3月20日 22:10
« 青いロマンス。 | メイン | [DTM作品] フライト・レコーダー »
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://birdwing.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/900

